
2025.9.30
以下のニュースが広がりました。
東京都はインターナショナルスクールの誘致・拡充に向けて支援をおこないます。
都は、東京の発展につなげるため、グローバル企業を呼び込むなどして、都内で、「高度専門職」などの在留資格を持つ外国人を2030年に5万人に増やす目標を掲げています。
この取り組みのひとつとして、東京に赴任した外国人への情報発信を強化するため、都内のインターナショナルスクールの情報を一元的に発信する専用サイトを来月、開設することを明らかにしました。
さらに、都内への進出や増設を検討するインターナショナルスクールの事業者に対し、事業計画の策定や申請手続きなどの包括的な支援をしていくということです。都によりますと、現在、都内には認可されたインターナショナルスクールが14校あります。
わかりにくいですけど、Kっていうのはキンダーガーデン(幼稚園)、9は中学校、
12は高校までって意味です。
なお、ここに乗っていないインターナショナルスクールもいっぱいあります。
怒られますけど、英語塾みたいなものですからね。
1. American School in Japan (ASIJ)
所在地:調布市
カリキュラム:米国式
対象:K–12
特徴:日本最大級、米国大学進学に強み
2. The British School in Tokyo (BST)
所在地:渋谷区・昭島市
カリキュラム:英国式(IGCSE, A-levels)
対象:Nursery–Year 13
特徴:英国系の本格教育、2キャンパス制
3. Nishimachi International School
所在地:港区
カリキュラム:米国式+IB
対象:K–9
特徴:多国籍、バイリンガル要素あり
4. St. Mary’s International School
所在地:世田谷区
カリキュラム:米国式+IB
対象:K–12(男子校)
特徴:名門男子校、スポーツ強豪
5. Seisen International School
所在地:世田谷区
カリキュラム:米国式+IB
対象:K–12(女子校)
特徴:名門女子校、カトリック系
6. International School of the Sacred Heart
所在地:渋谷区
カリキュラム:米国式+IB
対象:K–12(女子校)
特徴:歴史ある女子校、国際色豊か
7. Tokyo International School (TIS)
所在地:港区
カリキュラム:国際バカロレア(IB)
対象:K–12
特徴:急成長校、都心アクセス良好
8. New International School of Japan
所在地:豊島区
カリキュラム:米国式+二言語教育
対象:K–12
特徴:英日バイリンガル教育に特化
9. K. International School Tokyo (KIST)
所在地:江東区
カリキュラム:国際バカロレア(IB)
対象:K–12
特徴:学費控えめ、学力水準が高い
10. Montessori School of Tokyo
所在地:港区
カリキュラム:モンテッソーリ教育
対象:Pre–Grade 9
特徴:個別教育重視、少人数制
11. Christian Academy in Japan (CAJ)
所在地:昭島市
カリキュラム:米国式・キリスト教教育
対象:K–12
特徴:米国系伝統校、キリスト教色が強い
12. Lycée Français International de Tokyo
所在地:北区
カリキュラム:フランス式(仏教育省認定)
対象:K–12
特徴:フランス人向け中心、欧州大学進学に強い
13. Deutsche Schule Tokyo Yokohama
所在地:町田市
カリキュラム:ドイツ式
対象:K–12
特徴:ドイツ語中心、理系教育にも強い
14. Japanese International School (JIS)
所在地:練馬区
カリキュラム:英国式+国際カリキュラム
対象:小中中心
特徴:小規模でアットホーム
東京都は国際都市戦略の一環として、インターナショナルスクールの開業支援を打ち出しています。
土地情報の提供、行政手続きのサポート、既存校との交流促進など、外国人家庭が安心して東京に住めるよう環境整備を進めるという狙いです。
一見すると前向きな政策に見えます。
しかし、実際のインターナショナルスクールの現場を知る立場からすると、残念ながら東京都はインターの実情を十分に理解していないと言わざるを得ません。
国は「認めない」、都は「誘致したい」
そもそも国(文科省)の立場は一貫しています。
「インターナショナルスクールは一条校ではないため、就学義務を果たしたことにならない」
就学支援金の対象にもならず、補助金も出ません。
一方で東京都は、国際都市としての競争力強化のためにインター誘致を積極的に進めている。
高度人材や外資系企業を呼び込むには、インター整備が不可欠だからです。
この「国は線を引く、都は推進する」というねじれ構造は、教育制度の中でも際立った矛盾です。
実情①:高学年ほど生徒が減る
インターは小学校低学年までは在籍者が多いですが、
英語についていけない 学費負担が限界 日本の大学進学を考えて国内校に戻る
といった理由で、中高に進むほど生徒数が減少します。
高学年は運営がギリギリの学校も少なくありません。
実情②:「未来がない」と抜けていく家庭
保護者の中には「このままでは子どもの進学が不利になる」と考え、途中でインターを離れる家庭もあります。
「インター生は未来がない」という厳しい声が現場から聞こえるのも事実です。
実情③:開業支援はむしろ逆効果
東京都がさらにインター開業を後押しすればどうなるでしょうか。
生徒数が分散 → 各校がさらに経営不安定になる
質の確保が難しいま→ 教育レベルが低下
新設校と既存校の間で競争が起きるが、家庭の負担は変わらない
つまり、学校数を増やすことが、かえって教育の質を下げるリスクを孕んでいるのです。
本当に必要なのは「質の担保」
東京都が「国際都市の魅力」を高めたい気持ちは理解できます。
しかし、本当に必要なのは「数」ではなく「質」。
教員の確保と育成 国際的に通用するカリキュラムの保証 学費や進学ルートの透明化
こうした土台を整えない限り、インターナショナルスクールは「名前だけのブランド」にとどまり、保護者や子どもにしわ寄せが続くでしょう。
まとめ
東京都が進める「インター開業支援」は、一見すると華やかですが、現場の実情と大きな乖離があります。
「子どものために」と思って通わせた家庭が、将来に不安を抱いて途中で抜けていく現実を変えるには、まず教育の質の保証が欠かせません。
インターナショナルスクールは、都市戦略の道具である前に、子どもたちが未来を築くための学びの場であるはずです。
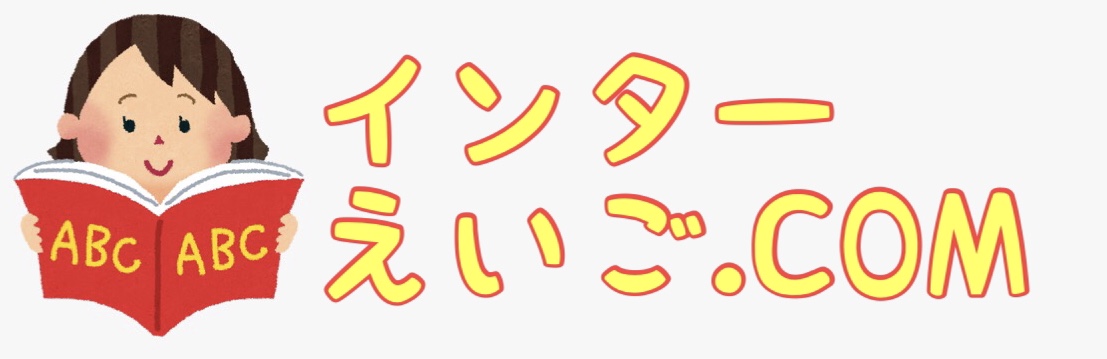

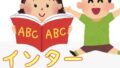
コメント